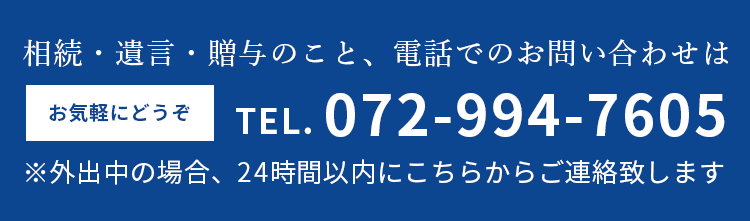Q&A
ホーム > Q&A
よくある質問をまとめました
あなたが気になることはありますか?
Qどのような場合に相続税が発生するのですか?
A原則として相続税の基礎控除額を超えれば相続税が課税されます。
相続税とはお亡くなりになられた方の「遺産の額」に対して課される税金です。
ここでいう「遺産の額」は現金や不動産等のプラスの財産から借金等のマイナスの財産を差し引いた差額を指します。
相続税は原則として、この「遺産の額」が「相続税の基礎控除額」を超えている場合に課されます。平成29年度現在の相続税法では「相続税の基礎控除額」を3,000万円+600万円×相続人の数と定めています。
例えば相続人が3人の場合3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となり、遺産の額が4,800万円を超えていれば、その超えた金額に対して相続税が課税されることとなります。
ただし、遺産の額が基礎控除額を超えているからと言って直ちに相続税が課せられる訳ではありません、相続税法では遺産の取得者ごとの特例を認めており、例えば配偶者(夫からみた妻、妻からみた夫)の場合、取得財産が1億6,000万円未満なら相続税を課さないという「配偶者控除の特例」が認められている為、取得者によっては相続税が免除されるという場合もあります。
そのような場合、相続税が発生しなくても“特例を使って”相続税が発生しないわけですから、相続税額0円で相続申告をしなければなりませんのでご注意ください。
Qなぜ税理士により相続税額が異なるのですか?
A相続税の計算方法が税理士により異なるからです。
相続税の申告を税理士報酬や人付き合いで安易に依頼される方がいらっしゃいますが、断言します「それは間違いです」。
税理士の中でも本当に相続税が得意な税理士は2%以下だと言われています。
理由は、税理士になるための試験科目にあえて難解な「相続税法」を「選択」(「相続税法」の試験科目は「選択制」です)した税理士は税理士全体の2%から3%であり、さらにその中で年1回あるかないかといわれる相続申告業務を日々こなしている税理士…となるとほとんどいないからです。
では、相続が得意な税理士とそうでない税理士とでは本当に相続税額が違うのでしょうか?
結論を言うと「全く」違います。
なぜなら相続税の計算方法が両者で「大きく」異なるからです。
例えば土地の評価一つにしても広辞苑のような専門書が書店で売られています。
その専門書に精通し、かつ実測・交渉のコツを知っている実務経験豊かな税理士と、そうでない税理士とで土地の評価額が異なるのはむしろ当然です。
土地や株式の評価額が違えばもちろん相続税額も異なってきます。
相続税の申告を税理士報酬や人付き合いで安易に依頼すると、その代償が相当なものとなってしまうかもしれません。
Q相続税対策はどのような場合に必要ですか?
A相続税対策が必要な方として特に以下のような方が考えられます。
・将来相続税の発生が確実な方
・将来相続人間で遺産分割が難航すると思われる方
・事業承継がまだお済みでない方
・不動管理会社の設立または経営についてお悩みの方
・不動産収入を得られている方
・大型の贈与を検討されている方
・土地活用についてアドバイスを求められたい方
・遺言について興味のある方
★上記の要件に複数当てはまる人ほど必要性は高くなります!!
※相続税対策はあくまで税金が相当額出る、又は、複雑な案件で必要があると認められる場合に行います。 わざわざ10万円を払ってまでシミュレーションする必要のない場合、こちらからお断りさせていただくことがあります。
Q依頼までの流れはどのようになりますか?
Aご依頼いただく際の流れは以下のようになります。
| 無料相談 | まずはご要望・ご依頼の内容をお聞かせ下さい。 電話、メール、FAXでお受けします。 |
|---|
| 報酬提示 | 見積書を電話、メール、FAXのいずれかの方法で当日中に御呈示させていただきます。 |
|---|
| ご了承 | 電話、メール、FAXでご了承のご連絡をいただきます。決してこちらから催促するような事はいたしません!! |
|---|
| 業務開始 | 今後の流れ等を具体的にご説明させていただきます。 プライバシー保護のため「秘密保持契約」を締結します。 |
|---|
松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください


難波支店
〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401
各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分
TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

梅田支店
〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F
京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分
TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892